2009年7月28日(火) |
通勤費をめぐる不合理 |
通勤費非課税規定 所得税法では通常の給与に加算して受ける通勤手当を非課税としています。実際、給与を得るのに従業員が何か仕事に不可欠な物・道具・その他の代金を負担するということはあまりありません。 例外は皆無 ただし、通勤費が10万円超のケースではその超過分は給与所得だとの規定があります。しかし、平均通勤費は1.6万円で、通勤費3.5万円以下で98%超、4.5万円以下で99.9%を占めており、通勤費10万円超該当者はほとんどいません。 10万円規定はズルく利用されることへの予防線にすぎません。通勤費完全非課税という実態認識を変える必要はないと思われます。 社会保険は不合理 ところが、社会保険や雇用保険や労災保険では通勤費について、必要経費の補てん金ではなく、給与収入の一部という扱いにしています。それで保険料負担の対象になっています。 年金・健保・雇保からの給付金を受けるようなときは通勤することがなくなっているときなのですから、給付額の中に通勤費に相当する部分が入っている必要はないはずです。 明らかな構造設計的論理矛盾です。 それに、能力が低いので給与も低い従業員だったとしても、遠距離通勤だったことにより、社会保険料の本人負担分、事業主負担分が増えて、その従業員の将来受給年金や雇用保険などの給付が多くなる、というのも納得し難いところです。 |
格差社会での派遣労働者は自己負担 税の規定は所得の実質主義に基づいているかのようではありますが、税の規定も形式主義で、通勤費名目でないものは非課税にならないようです。 派遣労働者の多くは通勤費補助がない人です。 しかし、彼らも通勤費を負担して通勤しており、その費用は受け取る給与によって償っています。同じ通勤費について、公務員や正社員は非課税、非正規労働者は考慮なしでは社会的差別の上塗りです。 通勤費非課税の規定の不平等取扱いを早急に改めるのは時代の要請です。 それとともに、社会保険の不合理性も税との取扱いの一元化の方向で改められるべきです。
|
||
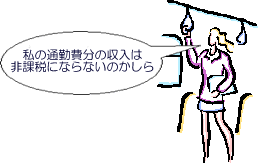 |
|||