2009年7月31日(金) |
通勤費をめぐる係争 |
通勤手当がないから 通勤手当が給与明細項目として設定されていないけれども、それを前提として給与の総額が定まっている場合、給与収入のうち月々の定期券代相当分については給与収入から外して、通勤費補てん額として費用としての通勤定期券代の相殺項目に振り替えて、所得税の確定申告をすることは認められるでしょうか。 氾濫的に係争がおきている 派遣労働者の多くが、収入項目に通勤手当のない給与明細を受け取っており、所得計算において通勤費をどう扱うかが社会問題となっています。 非課税扱い申告をして、否認され、係争になっている事例が報道されるようになってきました。 形式論理の課税庁 課税庁は修正申告を勧奨しているようですが、納得しない申告者が沢山出現しているようで、国税不服審判所での非公表審判事例が増えていそうです。 当局の主張は、通勤手当が通常の給与と区分して支給されていないので、非課税に該当する所得はない、とつれない内容です。 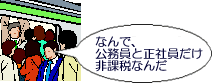
|
審判所の苦悩 審判所には大岡裁きをする能力がないようで、当局の論理を是としつつ、通勤手当が分別支給されていないという理由だけで課税対象にするのは不当という納税者の主張は、法令自体の当否を訴えていることであり、そういうことは審判所の権限を超えている、と裁判への誘導を促しています。 法律をよく読むと 通常給与と分別されている通勤手当の非課税の法律規定には、(これに類するものを含む)との注書きがあります。 公務員や正社員が優遇され、非正規労働者が冷酷なあしらいを受けることのないようにと配慮するとしたら、この注書きを幅広く解釈することは可能なはずです。 通勤費訴訟のうごめき 通勤費訴訟がサラリーマンの底辺を構成する多数の派遣労働者により、サラリーマン内部の矛盾の告発として、起こされつつあります。 制度の矛盾と日本社会の大企業正社員主義が危機に瀕していることを表象しています。 また、大岡裁きは可能でも、雇用主側の通勤費負担の制限強化等の社会反動になる可能性もあります。 当局も予測しかねて臆病になっているのかもしれません。 |
||
|
|||