2009年2月2日(月) |
もしも
事業主が裁判員になったら
|
日本税理士会連合会の機関紙「税理士界」 (2008年11月15日刊)に「裁判員制度の問題点」という会員寄稿がありました。 要約を抜粋的に紹介したいと思います。 辞退できるか 裁判員は選挙人名簿から無作為に選ばれ、原則的に逃れることができません。 ただし高齢者や要介護者を持つ者などは辞退が可能ですが、「仕事が忙しい」ということでは辞退事由に該当しません。 真に業務に重大な支障がある場合は「裁判所の判断により」例外的に辞退が認められるということです。 聞くところによれば 有名な俳優がドラマロケをする日であれば、代替不可のため辞退可能であり、有名ニュースキャスターが夜の番組のため昼間取材をする必要があるならこれまたおそらく辞退可能であるとのことです。 それに対して、例えば小規模鉄工所の社長が、納期が迫っている、ということでは辞退が困難ではないかといわれています。 他の人でもできるはずだ、とか他の日でも可能でしょう、と言って、まさに職業によって国民の等級付けをし、おそらく平均的な税理士関与先は「重要ではない仕事」とのレッテルを貼られるに違いありません。 |
辞退が認められないとどうなるか 辞退を認められないときは、自分の身体状況や仕事を犠牲にして裁判所へ出向くか、不出頭により自らがしかるべき法的制裁を甘受するか、の選択を迫られることになります。 税理士やその関与先の多くの中小企業にとって、経営者や従業員が一週間も職場から遠ざけられたら、まさに企業存亡の危機を迎えないとも限りません。 彼らがその候補に選ばれた年には、新しい仕事も控え、裁判員に当たった時には、裁判官に土下座して仕事の大変さを涙ながらに訴えるも拒否され、順法精神の強さから裁判所へ出掛け、その結果事業が取り返しのつかない大打撃を受ける、このような悲劇は珍しいことではなくなるかも知れません。 寄稿者のむすび 寄稿者は、もし国民と司法を近づけるための裁判員制度がどうしても必要であるというならば、せめて志願制にすべきである、と結んでいます。同感です。 なお、刑事裁判より税金訴訟ほかの行政裁判にこそ裁判員制度を導入し、司法行政の国民監視をすべきということを申し添えても置きたいところです。
|
||
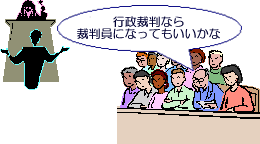 |
|||